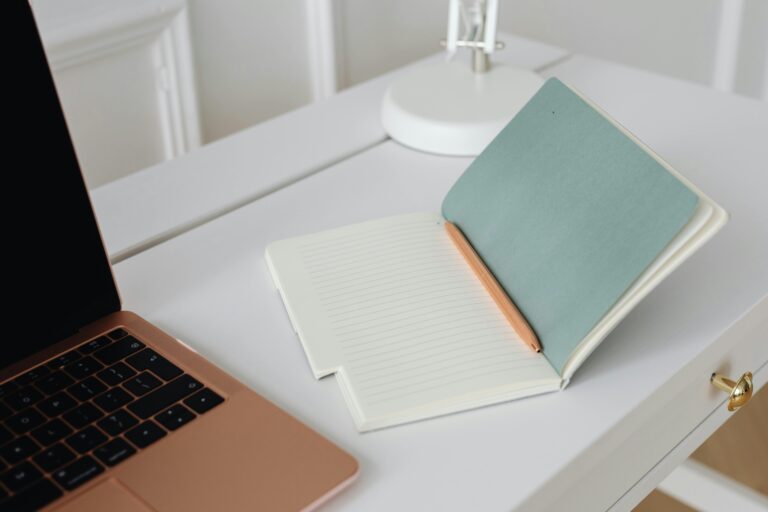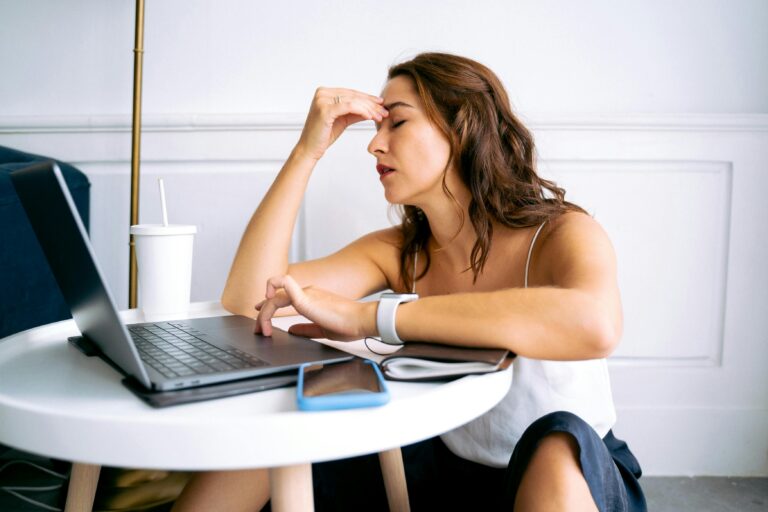話し上手な営業は印象が良く、聞き心地もいいものです。
でも実際に成果につながるのは、「話す力」よりも「伝えたことが共有されているか」。
共通認識が取れている営業こそ、信頼され、次の仕事につながります。

商談ではしっかり話しているし、説明もできている。
それなのに、「反応が薄い」「次につながらない」といった違和感を抱いたことはありませんか?
“話せている”のに、“伝わっていない”──営業の現場では、こうしたギャップが思った以上に成果を左右します。

営業は「売る人」ではなく、「一緒に成果をつくる人」へ──
そんなスタンスが、今の時代に求められています。
共感をベースにしつつも、“共創”の視点を持った営業スタイルが、新たな価値を生み出すのです。
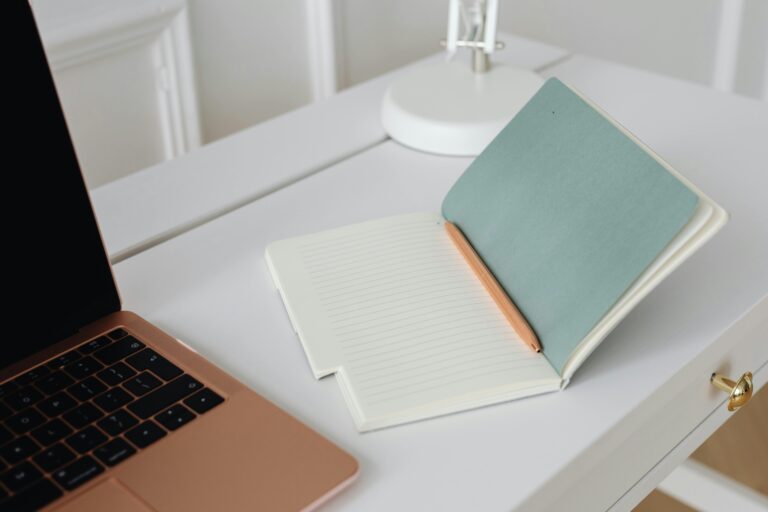
「相手を尊重したい」「押しつけにならないように」──
そんな思いから、つい提案が控えめになってしまうことはありませんか?
でも実際には、“やさしさ”と“遠慮”は紙一重。
提案を通して価値を届けるには、“自分の軸”が必要なのです。

「人間関係はいい」「信頼されている気がする」──
それでも、なぜか契約にはつながらない。そんな経験はありませんか?
実はそこには、“信頼と成果”をつなぐ“もう一歩”の設計不足が潜んでいることが多いのです。
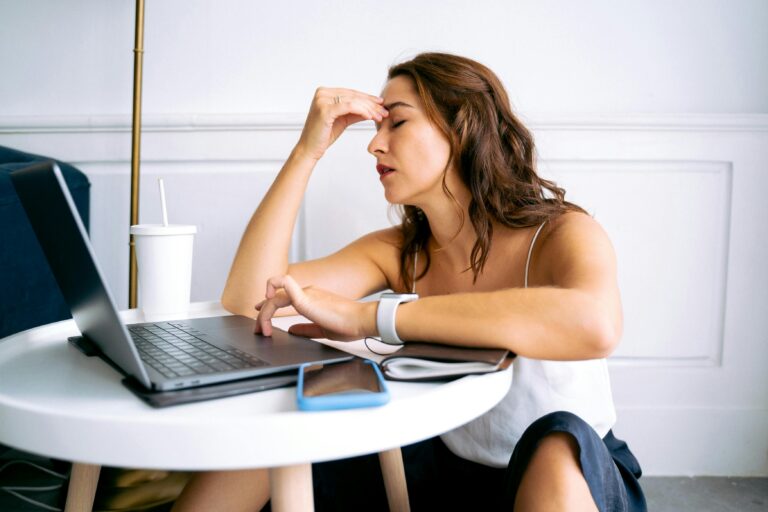
共感力は営業における強みですが、
ときにその強さが裏目に出て、「共感疲れ」「感情の巻き込まれ」を引き起こすことがあります。
特にフリーランスや支援業の現場では、相手の悩みや不安に触れる機会も多く、心がすり減りやすいのです。

共感力の高い営業パーソンは、相手に信頼されやすく、関係構築が得意です。
けれど一方で、「嫌われたくない」「関係を壊したくない」と思うあまり、本質的な提案を避けてしまうという悩みも多く見られます。

営業で大切なのは「相手に寄り添うこと」──
でもその意識が強すぎると、“合わせること”が目的化してしまい、結果的に成果から遠ざかってしまうことがあります。

営業において「わかります」の一言は、信頼をつくるうえで大切な入り口です。
けれど、「わかります」で止まってしまう人と、そこから一歩前に進める人では、結果が大きく分かれます。

営業で大切なのは、相手に共感するだけでなく、その共感をもとに「何が問題なのか」を明確にすること。
“課題の言語化”ができるかどうかで、提案の説得力が大きく変わってきます。