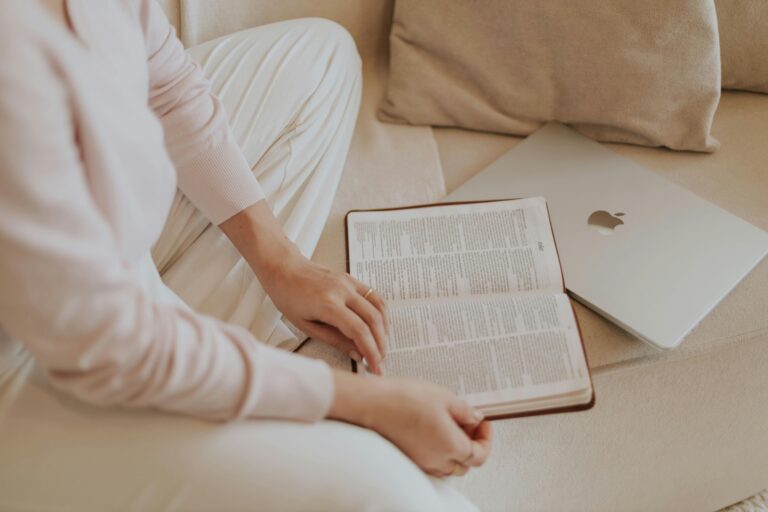「すごく動いてくれる時と、そうでない時の差が激しい」
「やる気がある時は頼もしいけれど、ムラがある」
そんな印象がついてしまうと、継続依頼にはつながりづらくなります。
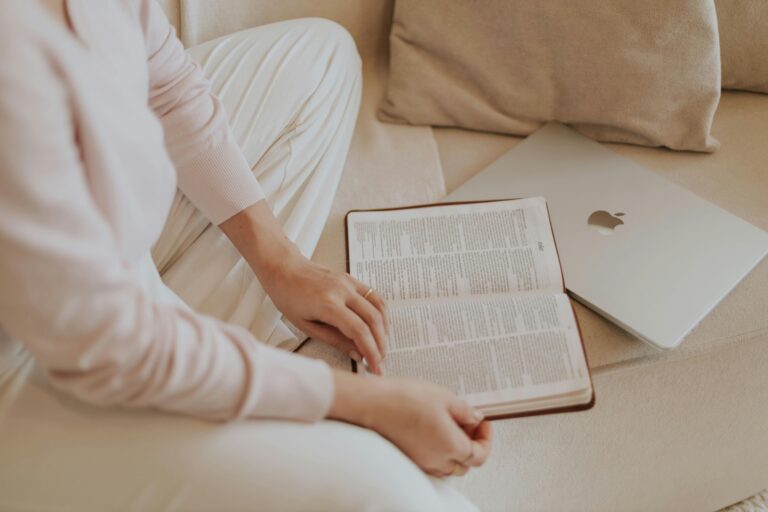
仕事が立て込む時期、予定が複数重なる時期でも、
“この人なら安心して任せられる”と思われる人には、共通して「スケジュールの整え方」があります。
実はスケジュール管理の巧さが、そのまま信頼残高を積み上げているのです。

どれだけ仕事ができても、体調不良が頻発すると、徐々に「任せにくい人」という印象がついてしまいます。
もちろん人間だから、誰にでも体調を崩すことはあります。
でも、“頻度”と“対応の仕方”が信頼に直結するのです。

スキルがあっても、経験が豊富でも──
「この人、いつも余裕なさそう」と思われた瞬間、仕事の依頼は遠のいてしまうことがあります。
成果そのものよりも、“その人の雰囲気”や“言葉の選び方”が、信頼や安心感を左右するのです。

KPI は個人が意識するもの——そう考えるチームもありますが、
本当に強いチームは“KPI を共有する文化”を持っています。
それは、成果の見える化だけでなく、関係性の質にも大きな影響を与えるのです。

報告や会話の中で、感覚だけでなく“数字”が自然と出てくるチームは、
高い成果を出しやすい傾向があります。
なぜなら、数字は共通言語として“判断と改善”を支えてくれるからです。

どちらも KPI として“正しく設計されている”ように見えても、
実際に回るチームと、動かなくなるチームが存在します。
その差を生むのは、KPI の“設計の細部”にあります。

KPI を設定する前に、本来必要なのは“仮説”。
何をすれば、どんな成果が出るのか?
誰に、どう届ければ、反応があるのか?
その仮説がないまま数字だけ決めても、空回りするだけなのです。

「頑張っているのに成果が出ない」
「指標は追っているのに手応えがない」
そんな時、KPI の設計そのものに“抜け落ちた視点”があるかもしれません。

営業チームや在宅の支援チームでは、
数値を軸にした評価制度が導入されがちです。
もちろん、成果を数値で示すことは公平性を担保する面もあります。
しかし、数字だけで評価すると“本質的な力”を見落とす危険性があります。